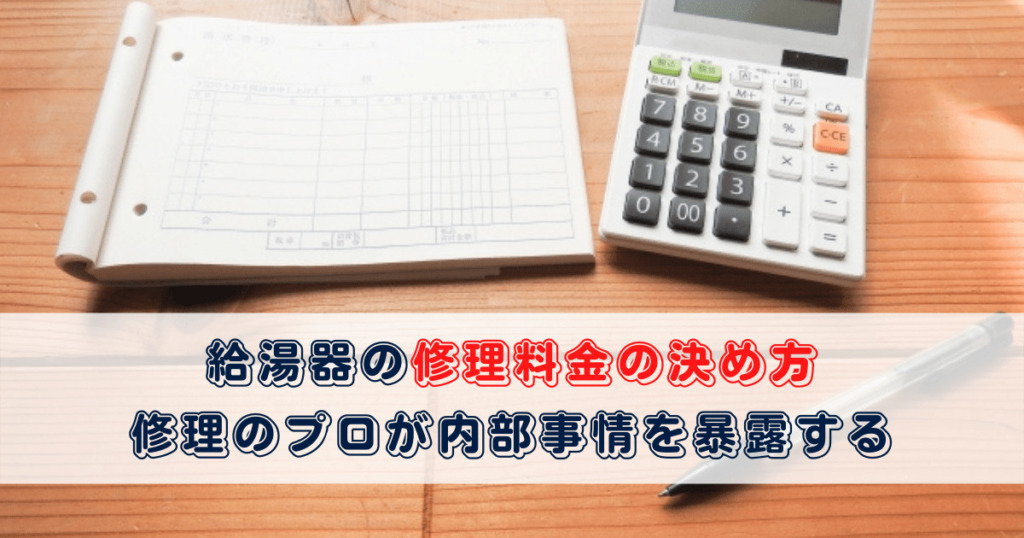
あなたは給湯器を修理する時に、修理業者の人に対して「ちょっと勉強してください」とか「ちょっと負けてください」というようなカタチで、いわゆる「修理料金を安くしてください」というお願いをしたことがありますか?実は給湯器の修理に来ている人間は厳密に言うとメーカーの人間ではないので、その人に価格交渉をしても無駄であることが多いです(この人には金額をどうこうする権限がないと言ってもいいです)。
じゃあ誰が決定権を持っているのか…・給湯器の修理料金がどのようにして決まっているかを理解することで、万が一「給湯器が早く故障してしまって納得がいかない!」ということが起こっても、然るべき価格交渉が出来るのではないかと思います。
そこで今回は「給湯器の修理料金の決め方」について分かりやすく解説していくので、給湯器の修理費用に関してトラブルになりそうだったり、価格の面で納得できないということがあったら、ぜひ参考にしてみてください。
給湯器の修理料金の決め方
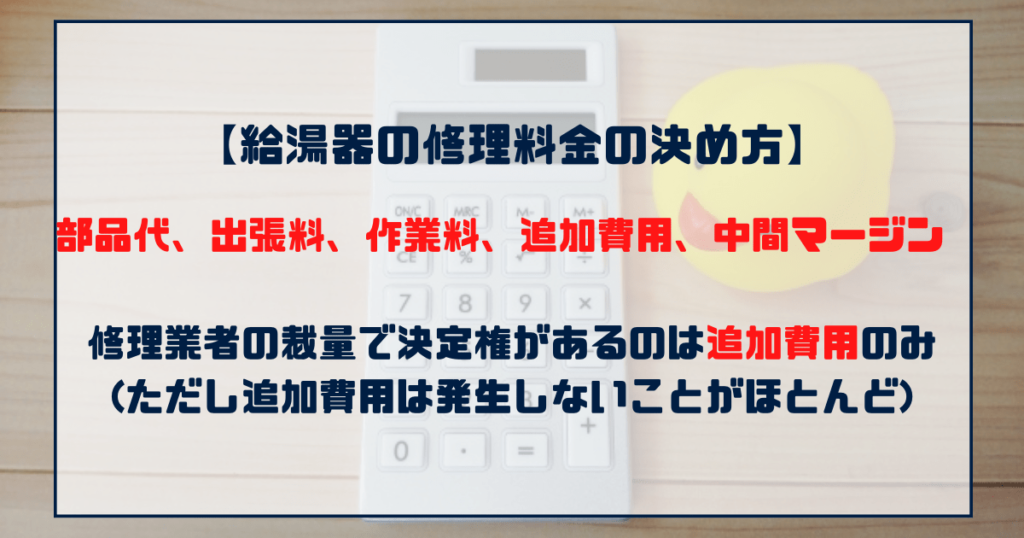
給湯器の修理に発生する費用は、主に上記の5点のトータル金額となります。
1~3は基本的な金額で、4、5については発生する場合と発生しない場合があるので、給湯器の修理費用を安くしたいという場合は注意が必要です。以下では1つ1つについて詳しく解説していきます。
部品代
給湯器の修理に必要な部品代金です。ちなみに部品代金が1000円だったとすれば「メーカー800円、修理業者200円」くらいの取り分になるのですが、実際にその部品を製造するのにいくら掛かっているかなどの細かい部分は、私たちも知らされていません。
よく「部品を丸々交換しないで分解調整などで修理できないのか?」と言われることがあるのですが、簡単に調整できる場合と出来ない場合があります。そして下手に調整をして「やっぱりすぐ壊れてしまって交換しなきゃダメだった」という場合に、お客さんとトラブルになることが多いので基本的には下手に手を加えずに交換することが多いです。
出張料

メーカーサービスが事務所を構えている場所から、お客さんの家までの距離に応じて出張料が掛かります。私が担当している都道府県では、弊社の事務所がある市内の現場なら2000円ちょっとで市外に出ると3000円程度という感じです。
基本的には20km以内か20km以上か等で区別されており、いくらメーカーサービスの事務所から現場まで遠いからと言っても、その距離に比例して青天井でお客さんに負担が増えるというシステムではありません。
お客さんのお家に修理訪問する以上は、例え修理をしないと言われても原則として「点検をするために伺った際の諸経費」ということで最低限この金額は発生します。修理に伺って診断させてもらい、お客さんの判断で「じゃあ修理しない」という判断になった場合、中には「修理していないんだからお金は払わない」という方がいますが、車両に乗って現場に行くだけでも費用は発生するということをご理解ください。
 こたろー
こたろーお客さん自身が故障した給湯器を事務所まで持ち込んでくれる場合(修理完了後も引き取りしてくれる場合)は、出張料は掛かりません。
作業料
ここについてはメーカーから「水通路部は1点につき8000円」「熱交換器は20000円」という感じで、メーカーによって料金が決められています。そして2点目の部品交換になると、基本作業料が半額になるという感じです。
例えば水通路部を3点交換するとなれば、8000円+4000円+4000円=16000円となります。そして修理作業量には基本上限が設けられており、ノーリツ製給湯器の場合であれば原則として1回の修理で20000円を超えることはありません。
追加費用
- 製品脱着作業が必要な場合
- 作業スペースが狭く、著しく作業効率が低下する場合
- 高所に設置されている場合
ここが少し厄介なのですが、例えば「設置状況があまりにも悪くて、修理に取り掛かるまでに時間が掛かる」とか「設置されている給湯器をその場で修理できず、取り外して外に引っ張り出して修理する必要がある」等の場合、作業料の上限でやれと言われると割に合わないという場合があります。
このように給湯器内部の直接的な修理費用以外の部分で費用が発生する場合は、各修理スタッフの裁量で請求金額を上げても良いということになっています。ここについては修理する側も「いたずらに金額を上げてやろう」という感じでは請求額を上げたりしません。
むしろ「別途料金はできるだけ発生しない方が望ましい」という気持ちが強いので、ここを下げてもらうために価格交渉をするというのは難しいでしょう。



設置状況が悪いせいでお金が掛かるという場合、それを正直に言ってしまうと「お客さんが施工店に文句を言う→巡り巡って施工店からクレームがくる」ということもあるので、お茶を濁すようなカタチになるケースも少なくありません。
中間マージン(直接依頼じゃない場合)
給湯器が壊れてしまったという時に、お客さんが最初にどの業者に修理依頼したかによって中間マージンを取られてしまうことがあります。給湯器は基本的にメーカーサービス(メーカーと直接契約をしている修理業者)しか修理できないので、ガス屋さんや設備屋さんに修理依頼の電話をしても、実際に修理に来てくれる人はメーカーサービスです。
この場合は「お客さん→業者A→メーカーサービス」というカタチになり、メーカーサービスが修理料金を請求する先は業者Aとなるパターンが非常に多いです。
もちろん「修理料金はお客さんと直接やり取りしてくれ」というパターンもありますし、私たちが請求した本来の金額を業者Aがそのままお客さんに請求するというケースもあるのですが、修理料金の10%~20%くらいを上乗せされていることが少なくないと言えるでしょう。


給湯器の修理費用を安くする方法(安く出来るかもしれない方法)
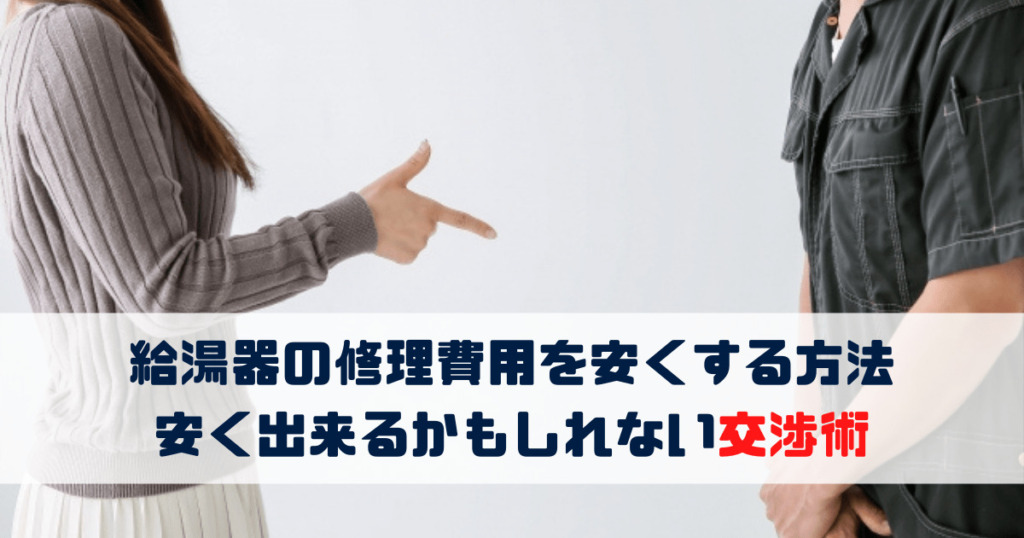
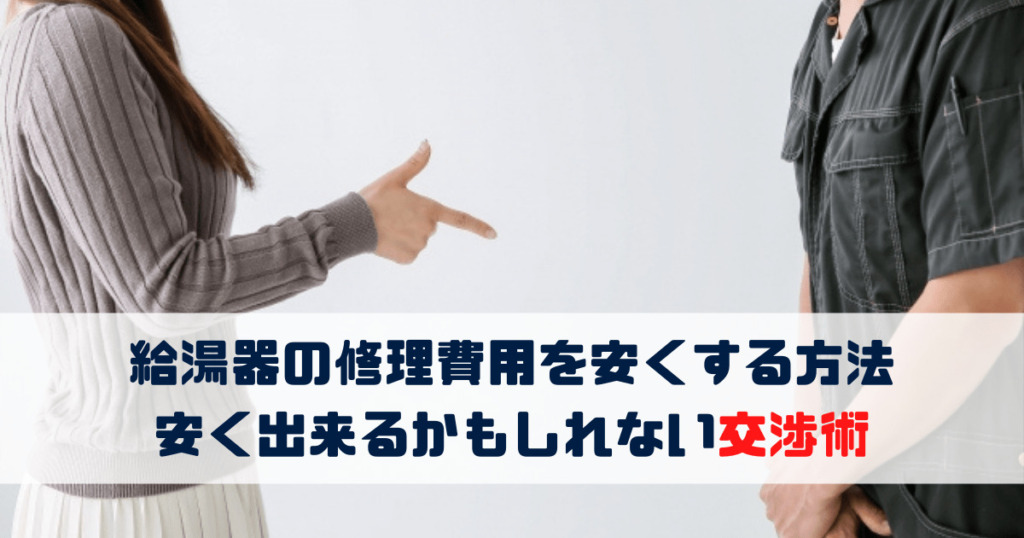
「あまりにも早い段階で故障してしまった(使用から3年以内、前回修理から2ヶ月以内など)」というケースであれば、修理費用を安くすることが出来るかもしれません。この場合は給湯器を取り付けてくれた業者やお家を建ててくれたハウスメーカーを通して修理依頼をし、納得できない旨をそれらの中間業者にぶつけることで「中間業者がメーカーに直接文句を言ってくれる可能性」が出てきます。
私たち修理業者は、自分たちの権限で値引きすることはできません。しかし立場的には修理業者の上にいるメーカーの営業担当者などが「修理費用はお客さんじゃなくてこっちに請求してくれ」という指示を出してくることがあるので、そうなればお客さんには請求が上がらないことがあります。
なんでもない修理でこのような中間業者を介してしまうと中間マージンを取られてしまう可能性がありますが、クレーム事案に繋げる場合は「お客さんvs修理業者」では話が発展しにくいことが多いので、こういう場合はハウスメーカーなどの力を持っている業者に頼るのが得策です。


給湯器の修理料金の決め方 まとめ
給湯器の修理料金は「部品+出張料+作業料+その他費用+中間マージン」から構成されている
基本的に修理するスタッフ本人には値引きの権限が与えられていない
クレームを言いたいような事例の場合は、あえて力のある業者を味方につけると吉
この世界にいると痛感するのですが、大人しく請求金額を払ってくれるお客さんが損をしているというイメージです。騒げば騒ぐほど「厄介だから値引きしよう」という風潮が強いと言っても過言ではありません。
しかしこの場合は、お客さんと修理スタッフでやり合うよりも修理スタッフの上にいるメーカー営業担当者をいかに引っ張り出すかの方が重要です。私たちも営業に「お客さんが納得してくれないんですけど何とかなりませんか?」と言ったりもしますが、基本的には「納得させるのがお前たちの仕事だろ」と言われて終わりなので。
これがハウスメーカーから言われたとなると請求先がコロッと変わったりすることも珍しくないので、どうしても納得できないようなカタチであれば、そっち方面から攻めてみてはいかがでしょうか。
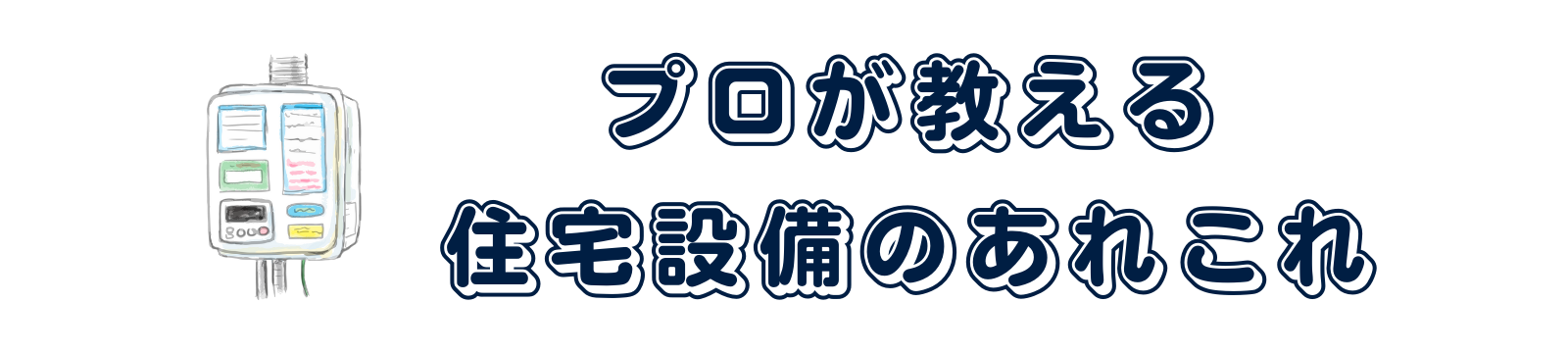
コメント